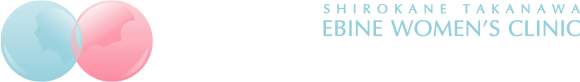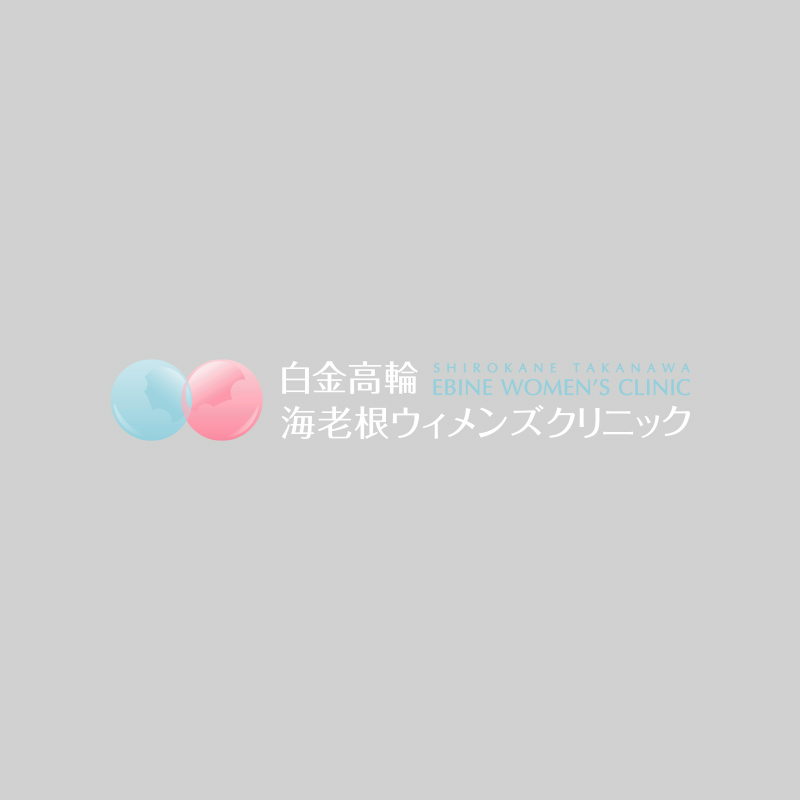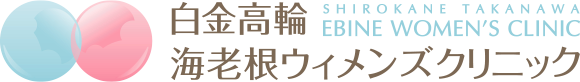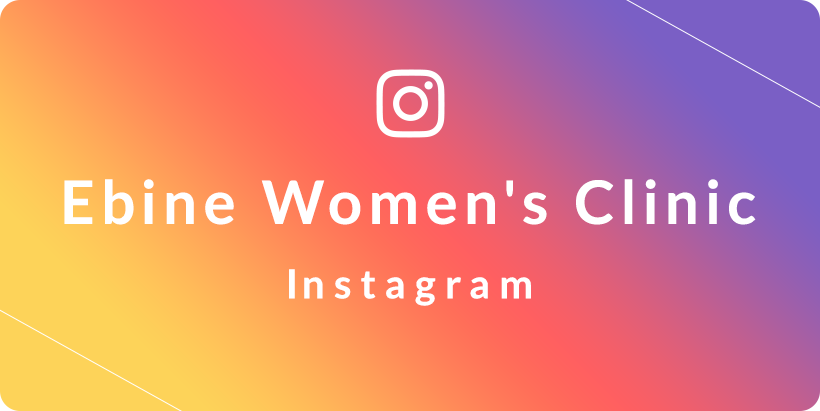梅毒の初期症状は?女性が注意したい妊娠妊婦への影響、類似する病気など梅毒を女医が徹底解説。
更新日:2025.10.29

女性の梅毒症状とは?
初期症状から治療、放置の危険性まで解説 ここ数年、梅毒の感染者数が非常に増えているということを、ご存じでしょうか?
とくに女性は20代での感染が非常に多くなっています。先天梅毒といって、胎児へ梅毒が感染する事例も増加しており、大きな社会問題だと感じます。
今回は、梅毒について、症状や感染経路、治療など、知っておいていただきたい知識をまとめました。思い当たる症状のある方は、ぜひ早いうちに婦人科でご相談ください。
20代女性の梅毒感染者が増加!
最新の梅毒情報
【20代女性は必読】梅毒の流行が過去最多レベル‼
目次
梅毒とは?
 梅毒の基本的な情報について、まずは整理しましょう。
梅毒の基本的な情報について、まずは整理しましょう。
梅毒の原因
梅毒トレポネーマという、らせん状の細い糸のような形をした病原体により引き起こされる感染症です。1911年に野口英世が梅毒スピロヘータの純粋培養に成功したのは有名ですよね。
梅毒はあらゆる性的な接触をきっかけとして、口や性器などの粘膜や皮膚から感染します。また、一度感染したら体に免疫ができるということはなく、感染者との性的接触があれば、何度でも感染します。
梅毒の感染経路
梅毒は、基本的に性的な接触のみで感染します。
・腟への挿入
・アナルセックス
・オーラルセックス
・性器へのタッチング
・キス
性行為による粘膜の接触が主ですが、感染者の精液・腟分泌液・血液などが傷口に触れて感染する場合もあります。
近年の梅毒増加と女性の感染者数
出典:厚生労働省ホームページ
日本では、1948年から梅毒患者の全数報告が開始されました。1960年ごろをピークに患者数は大幅に減少し、2012年ごろまでは年間1,000件ほどの報告しかありませんでした。実際、私が大学病院で勤務していた10年間、梅毒の患者さんが受診されたのはたった1人。ですが、ここ数年は本当に増えてきています。
性感染症というと「性風俗産業に従事している人」や「パートナーがたくさんいる人」の病気のように思われがち。ですが、感染した方の40%程度は性風俗産業への従事歴がない、ごく普通の女性ばかりだと報告されています。実際に私が診療した梅毒の患者さんは、普通の患者さんばかりです。
2013年ごろから徐々に感染者数が増え、2017年〜2020年は年間6,000件ほどの感染報告数で推移していましたが、2021年から急激に感染が拡大し、2023年には15,000件の感染報告がありました。そのうち女性は5,000件ほどで、ほとんどが20代です。
梅毒の歴史と野口英世

梅毒は、15世紀にヨーロッパで大流行し、日本にも16世紀に伝わってきた感染症です。元々は「美しい女性から感染する病気」として、ある種のステータスのように思われていました。
日本でも江戸時代には非常に感染が多くなり、とくに遊郭では梅毒が猛威を振るいました。
最近ヒットした「鬼滅の刃」という漫画でも、遊郭で梅毒が大流行していた時代背景を反映したキャラクターが描かれています。江戸時代の遊郭では、梅毒だけが原因ではないでしょうが、多くの遊女が22歳には亡くなっていたそうです。
梅毒の治療法はなく、今ではほとんど見られないような神経梅毒にまで至る方、梅毒で亡くなる方も多い時代が、長く続きました。
梅毒の治療の発展には、千円札の肖像にも採用された細菌学者「野口英世」が大きく貢献しています。
野口英世は、1911年に梅毒トレポネーマの培養に成功して世界的に知られるようになり、そして、1913年には「進行性麻痺・脊髄癆」が梅毒による症状だと証明したのです。
その後、1940年代にペニシリンが発見され、梅毒は「死の病」から「治る病気」へと変わりました。
梅毒の症状
 梅毒は、症状が出たり消えたりするため、感染の自覚がない場合が多くあるというのが最大の特徴です。「無症状だから梅毒に感染していない」とは言い切れません。梅毒の症状について、その時期と合わせてご紹介いたします。
梅毒は、症状が出たり消えたりするため、感染の自覚がない場合が多くあるというのが最大の特徴です。「無症状だから梅毒に感染していない」とは言い切れません。梅毒の症状について、その時期と合わせてご紹介いたします。
I期梅毒
感染後3〜6週間程度の時期に、まずは感染部位にしこりや潰瘍ができたり、鼠径部(足の付け根)のリンパが腫れたりといった症状が出ます。 この時期のしこりは「初期硬結」と呼ばれ、痛みはなく、小さく硬いのが特徴です。
次第に潰瘍化し、中心部が凹んだ「硬性下疳」となります。I期の症状は感染の部位に生じるため、女性であればデリケートゾーンや口唇にできることが多いです。 治療をせずとも、数週間程度で自然と軽快します。これが、感染を蔓延させる原因です。
II期梅毒
感染後数か月の時期には、手のひらや足の裏、背中、下腿などあらゆる箇所にバラ疹と呼ばれる特徴的な淡い赤の発疹が出てきます。梅毒トレポネーマが血流に乗って全身に回ることで、II期以降は全身に症状が出るようになります。
その他の皮膚・粘膜症状として、丘疹性梅毒疹、粘膜疹、扁平コンジローマなども特徴的です。扁平コンジローマは、脇の下、乳房の下、肛門の周囲やデリケートゾーンなど、皮膚同士が擦れるような部位によく生じます。
II期梅毒の皮膚症状も数週間程度で自然と消えてしまいますが、治癒したわけではありません。
潜伏梅毒
II期のあとの時期です。感染から1年以内(早期潜伏梅毒)であれば感染性があるといわれています。1年以上経過(後期潜伏梅毒)していれば、性行為での感染性はほとんどなくなります。 II期梅毒を過ぎてからは症状のない期間が非常に長く続き、体内ではゆっくりと病気が進行していきます。
III期梅毒(晩期顕性梅毒)
感染から数年〜数十年の月日を経て、ゴム腫、大動脈瘤や大動脈弁逆流症などの心血管梅毒、脊髄癆や進行性麻痺などの晩期神経梅毒と呼ばれる症状が出てきます。 梅毒で「鼻が落ちる」と聞いたことはないでしょうか?
これは、ゴム腫による「鞍鼻(あんび)」と呼ばれる症状です。
ゴム腫は周囲の組織を破壊するため、鼻の皮膚や骨が変形し、中央が凹んで落ちたように見えたことから、このように言われていました。 現在は、ペニシリンによる治療が可能になっているため、早期に診断できればここまで進行する方は稀です。
女性は症状に気がつきにくい?
梅毒は全身に症状が出るため、性感染症の中では比較的症状がわかりやすいものではありますが、女性のデリケートゾーンは目で確認しにくいため、症状に気がつきにくい場合もあるでしょう。
体を洗うときなど、デリケートゾーンに触れて「しこりがある」「デキモノがある」と気がついたときには、鏡などでよく確認してみましょう。デキモノが1個、2個程度であれば粉瘤や毛嚢炎も考えますが、複数のデキモノが同時にできた場合は、梅毒やヘルペス、コンジローマなどを疑います。
梅毒と似た症状が出る病気は?
 梅毒と似たような症状が出る病気としては、次のようなものが考えられます。
梅毒と似たような症状が出る病気としては、次のようなものが考えられます。
性器ヘルペス
デリケートゾーンに複数のデキモノが生じる病態としては、性器ヘルペスもあります。梅毒による初期硬結はとは異なり、ヘルペスによるデキモノは柔らかく、中に液体が含まれた「水疱」です。また、ヘルペスの場合は痛みも強く、水疱が破れるとかさぶたになる点も異なります。
ニキビや毛嚢炎
ニキビや毛嚢炎も、顔やデリケートゾーンに生じるデキモノとして、勘違いされやすいです。梅毒による初期硬結や 硬性下疳は、ある程度の期間が経過すると自然に消えるという点も、勘違いされやすい要因なのでしょう。 ニキビや毛嚢炎は、触ったり押したりすると痛みが出るという点が、梅毒による症状とは大きく異なります。また、一度に複数のニキビや毛嚢炎が生じることは少ないです。
蕁麻疹
バラ疹や丘疹性梅毒疹と見た目が似た病態の1つが蕁麻疹です。バラ疹は症状が数週間に渡り続きますが、一般的に蕁麻疹は数時間以内、長くても1日程度で症状がおさまる傾向にあります。
乾癬(かんせん)
「乾癬」という、慢性的な皮膚疾患があります。
皮膚に赤く盛り上がった紅斑が生じ、白色の鱗屑(鱗のようなかさぶた)で覆われる病態です。頭部、肘・膝、臀部、手のひらなどに症状が出やすく、半数の方はかゆみも伴います。 梅毒でも、「梅毒性乾癬」という乾癬に似た皮膚症状を呈することがあります。ただし、乾癬は手のひらや足の裏には基本的に症状が出ないのに対し、梅毒の症状は手のひらや足の裏にも出る点は大きな違いです。
女性が特に気をつけたいこと
 次のような点については、特に知っておいてください。
次のような点については、特に知っておいてください。
パートナーとのピンポン感染
パートナーとの間で病気をうつし合うことを「ピンポン感染」と呼びます。
梅毒に限ったことではありませんが、性感染症は、「パートナーと一緒に治療する」ことが非常に大切です。自分だけが治療をしても、パートナーは感染したままであり、性行為をするとまた感染を繰り返してしまいます。
性感染症を相手に伝えるのが難しい、ということはよく理解できます。不貞行為などが原因で感染するケースもありますが、全てがそうではありません。「感染に気が付かないまま何か月も経過し自覚症状もない」という場合も、感染性のあるケースが多く、感染の時期がなかなか断定できないのです。
感染がわかったら、まずは性的な接触のあるパートナーに伝え、検査を受けてもらいましょう。
妊娠中の梅毒感染は「先天梅毒」のリスク
2024年は、30例の先天梅毒の報告がありました。
(※出典:国立感染症研究所ホームページ)
梅毒に気が付かないまま妊娠したり、妊娠中に新たに梅毒に感染したりすることで、母体から胎児へと感染します。母体が梅毒の治療をおこなっても、胎児への母子感染を完全に予防することはできません。 しかしながら、早期発見は大切です。
妊娠初期に行う血液検査の推奨項目には梅毒の血液検査も含まれますので、必ず検査しましょう。次のようなさまざまな症状により、胎児への影響が非常に大きいため、妊娠4か月の検診で、全員に梅毒の抗体検査をおこないます。
【先天梅毒の影響】
・早産
・流産
・精神発達遅滞
・骨の異常
・心奇形
・難聴
・失明(網膜症)
・水疱状/斑状発疹
もちろん、女性だけが気をつけていても先天梅毒は防げませんので、パートナーの方にも先天梅毒の危険性を理解し、行動に気をつけていただく必要があります。
定期的な受診・検査も有効
気になる症状が出てからの検査でも、もちろん構いませんが、定期的な婦人科受診・検査も有効です。
症状がない期間も、感染して1年以内の期間は、性行為による梅毒の感染性があります。母子感染については、感染からの期間に関係なく、感染性があります。
パートナーが変わるとき、結婚するとき、妊娠を考える前などのタイミングで、梅毒の感染がないかどうか、確認するのがおすすめです。また、性的な接触のあるパートナーが複数いる方は、無症状でも定期的に検査をするのがよいでしょう。
ただし、一般的には自費の検査となります。 当院では、梅毒をはじめ複数の性感染症を同時に検査できる「STD性病検査セット」、子宮や卵巣の状態と性感染症などを調べる「ブライダルチェック」を用意しております。
梅毒の検査と治療方法
 梅毒の検査と治療について解説いたします。
梅毒の検査と治療について解説いたします。
梅毒の検査
梅毒の検査は、採血が必要です。ほかの感染症も疑う場合は、おりものの検査もおこないますが、梅毒だけであればおりものの検査はいたしません。
TP(梅毒トレポネーマ抗体)及びRPR(非トレポネーマ脂質抗体)の2種類の結果により、現在感染しているか、過去に感染していたかなどを判断いたします。
|
|
|
|
|
- |
- |
梅毒ではない、または感染初期 |
|
- |
+ |
生物学的偽陽性(※) |
|
+ |
- |
治療後の梅毒、後期潜伏梅毒 |
|
+ |
+ |
活動性梅毒、潜伏梅毒 |
※生物学的偽陽性:膠原病、悪性腫瘍、HIV感染、妊娠中などの要因で偽陽性となるケースがあります。
TPは感染から1〜2か月、RPRは感染から4週間程度は、感染していても陽性になりません。ですから、「陰性だけど梅毒感染が疑わしい」という場合には、時間をおいて再検査をおすすめします。
梅毒の治療法
ペニシリン系による治療が基本です。保険診療でおこなえます。アレルギーのある方は、別の薬剤で治療いたします。
・アモキシシリン(内服薬)
1回500mgを1日3回、28日間服用します。
・ベンジルペニシリン(注射薬)
早期梅毒であれば1回、後期梅毒であれば1週間ごとに3回、筋注します。
梅毒の治療で注意したいのは、ペニシリンを使用後に発熱や頭痛、発疹などの反応がよく起こるという点です。「ヤーリッシュ・ヘルクスハイマー反応」というもので、アレルギーとは異なりますので、治療を中断せず、継続していただく必要があります。
治療後は、治癒したかどうかの確認のため定期的に血液検査をする必要があります。指示した時期に、再度のご来院をお願いしております。
梅毒に関するQ&A

梅毒に関連して、よくあるご質問にお答えします。
Q. 梅毒の感染経路に心当たりがありません。性行為以外で感染する可能性はありますか?
梅毒は、あらゆる性行為(腟への挿入、キス、オーラルセックス、性器のタッチング等)で感染しますが、それ以外の日常生活で感染することはほとんどありません。
ただ、症状が出たり消えたりする点、自覚症状の全くでない時期がある点から、「いつ感染したか」とはっきりと断言できないため、心当たりがない、感染経路がわからないという方も、多くいらっしゃいます。
Q. 梅毒でデリケートゾーンがかゆくなることがありますか?
基本的に、梅毒による初期硬結やバラ疹などはかゆみ、痛みを呈しません。しかし、梅毒のほかに淋菌感染症などを併発していることもありますので、「デリケートゾーンがかゆいから梅毒ではない」と断定することもできません。
まとめ
今回は、梅毒の症状や感染者数の推移、歴史、治療などについて幅広くご紹介しました。
近年、梅毒の感染はかなり拡大しており、誰でも感染しうる病気となっています。皮膚症状が自然に消退したとしても、治癒したわけではありません。現在では稀ですが、進行すると鼻が落ちる「鞍鼻(あんび)」や神経症状など、多彩な症状が現れます。
症状がある方またはご心配な方は、早めの受診をおすすめいたします。また、定期的な検査もご検討ください。梅毒は、ほっておくと死に至りますが、治癒できる性病です。
関連リンク

白金高輪海老根ウィメンズクリニック院長
海老根 真由美(えびね まゆみ)
産婦人科医師・医学博士
埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センターでの講師および病棟医長の経験を積み、その後、順天堂大学で非常勤准教授として活躍。
2013年に白金高輪海老根ウィメンズクリニックを開院。
女性の人生の様々な段階に寄り添い、産前産後のカウンセリングや母親学級、母乳相談など多岐にわたる取り組みを行っています。更年期に起因する悩みにも対応し、デリケートなトラブルにも手厚いケアを提供しています。